こんにちは、あるいはこんばんは、「家事したくない」諸君。
『ない家事研究所』の Tanjism(タンジズム)だ。
「したくない」家事に時間を奪われない人生を送るためには、
ステップ1で、 自分の「したくない」家事を知り
ステップ2で、 やり方を根本的に見直し
ステップ3で、 実践し振り返る
→「したくない」家事に時間を奪われない人生を送りたい!簡単実践3ステップ
ステップ2で洗濯のやり方を根本的に見直した諸君は「今すぐにでも洗濯乾燥機が欲しい!」と思ったに違いない。
しかし、洗濯乾燥機は決して安い買い物ではない。
洗濯機選びに失敗したとしても、すぐに買い直すのは難しいはずだ。
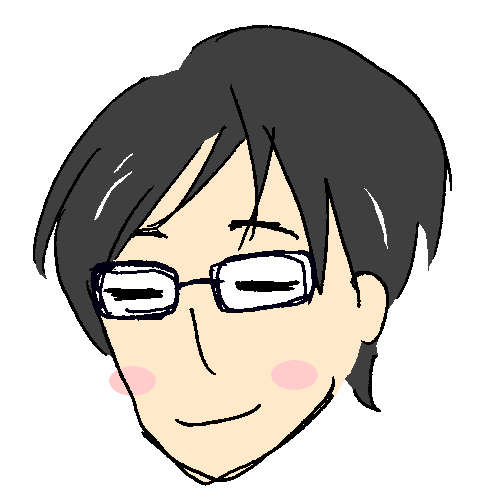
私の家では洗濯乾燥機を導入したことで、
飛躍的に洗濯の時短が可能となった。
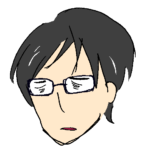
が、しかし…
思いもよらぬトラブルが発生し、そのトラブルを抱えたまま使い続けた経緯がある。
その教訓をもとに現在は2代目の洗濯乾燥機を選び、今のところトラブルなく使っている。
自分が求めるすべての要素が完璧な洗濯機など、そもそも存在しないかもしれない。
私の経験のように、実際に使ってみないと分からないような落とし穴があるかもしれない。
ただ良い点だけでなく、イマイチな点も知っていれば、理想の買い物に近づけるはずだ。
・カタログの情報だけでは分からないようなこと
・どんなことに気をつける必要があるか
実際に私が経験したことをもとに紹介する。
洗濯乾燥機を探す前に、まずはこの記事を読んで、諸君の頭の中に注意点を入れておいてほしい。
定期的な修理依頼が必要な場合もある

まず冒頭に話した『トラブル』について説明しよう。
時は2015年にさかのぼる。
当時は乾燥機能の無いシャープ製の縦型洗濯機を使用していた。
特に気になるトラブルは無かったのだが、引っ越しや家族が増えるタイミングで、洗濯乾燥機の導入を検討していた。
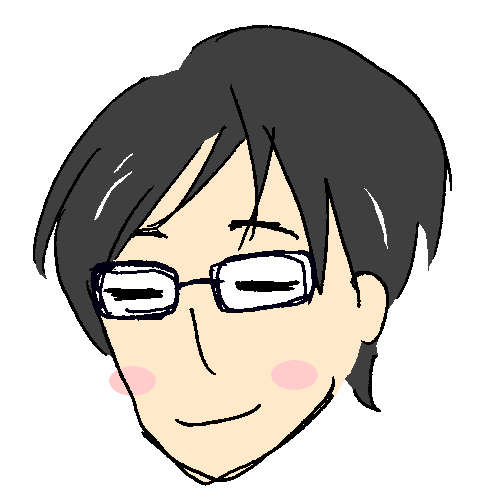
当時はドラム式のスタイリッシュなデザインや、『干す』家事から解放される喜びでワクワクしていたのを覚えている。
機種の選定についてはプロに任せるのが一番だと思い込み、
私自身での下調べはほぼせず、
家電量販店で店員さんにアドバイスを頂きながら購入した。
そして、東芝製 TW-Z96V2MLW に決めた。
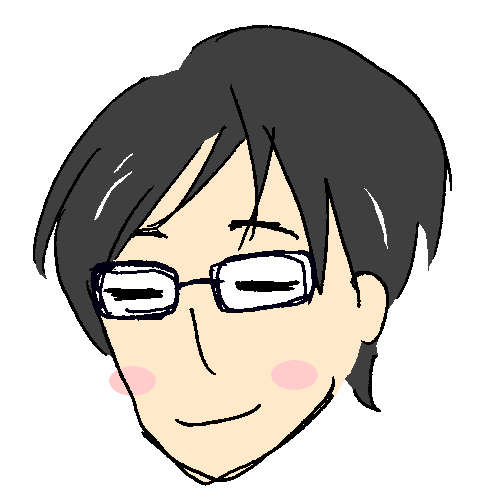
実際に使用してみると、最高の買い物だと思った。
夜寝る前にタイマーをセットすれば、朝には昨日の洗濯物が乾いているのだ。
仕上がりもふんわりしているし、思ったほどシワも気にならない。
これで本当に『干す』家事から解放される
…そう思っていたのだが。
1年後、最初の修理依頼
洗濯乾燥機を導入すると、洗濯時間が大幅に短縮され、生活にゆとりが生まれるようになった。
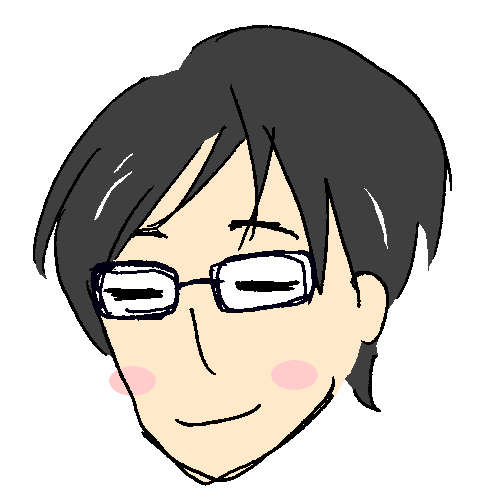
これで家事を「しない」理想的な人生に近づいた…
と、思っているのも束の間。
購入から1年ほど経って、あることに気付く。
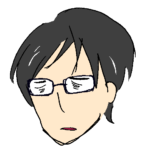
なんか、生乾きじゃない…?
気のせいかもしれないが、以前よりも洗濯物の仕上がりが湿っぽいような感じがしたのだ。
当初は、洗濯物の詰め込み過ぎが原因だろうと思い、洗濯物の量に気を付けてみた。
しかし洗濯物の量を減らしても、以前のようにカラッと乾かない。
マニュアルを元に、各フィルターを清掃するが、それでも改善しない。
むしろフィルターには、なぜかあまりホコリが溜まっていない。
そして徐々に悪化していき、最終的には乾燥後に『干す』必要が出てきた。
これでは何の意味も無い。
まだ保証期間中ということもあり、購入した家電量販店へ連絡。
出張修理に来て頂いた。
原因は内部ダクトへのホコリの蓄積
来て頂いたサービスの方の迅速な対応で、1時間ほどで作業は完了。
そして見せられた『巨大なホコリの塊』。
どうやら乾燥用の内部ダクトに詰まっていたそうで、コレが原因で送風が出来ずに乾燥不良になってしまったようだ。
なぜかフィルターにホコリが溜まっていなかったのは、これのせいだったのだ。
サービスの方がお帰りになった後、恐る恐る洗濯物を乾燥させてみた。
すると、購入当時のようにカラッと乾き、乾燥機能が蘇っていた。
これで安心して使える…
と思いきや、残念ながらこの現象は1、2年に一度の頻度で再発を繰り返すことになる。
結局のところ、構造上の問題
2度目の出張修理の際、サービスの方に聞いてみた。
とのことである。
つまり、この現象に関しては定期的に修理依頼が必要だということだ。
このように内部にホコリが溜まってしまう現象は、他メーカーや他機種でも発生するそうだ。
しかしユーザー自身で取り外し可能だったり、メンテナンス性の改善などが図られているものも存在するらしい。
つまりこの問題は構造上仕方のない問題なのだが、「定期的に修理依頼が必要」ということは、設計不良だと、私は思っている。
結局2023年に買い替えるまでの8年間で、他の修理も含めて6回ほど出張修理を依頼することになった。
現在では各メーカーの改良が進み、この問題は改善されているかもしれない。
しかし最新機能の追加などで構造が複雑化し、他の問題が潜んでいる可能性もある。
保証やサービスの面で、購入するのはネットではなく家電量販店でも良いと思う。
しかし購入する前には、自分でネットのレビューやトラブル記事を読んで、実際に使っている人の声(特にマイナス意見)を聞いておくことを強くオススメする。
乾燥が苦手な機種もある

まず洗濯乾燥機と聞くと、ドラム式を思い浮かべる人が多いはず。
しかし実を言うと、縦型洗濯機にも乾燥機能を搭載したものもあるのだ。
↓縦型洗濯機

↓ドラム式洗濯機
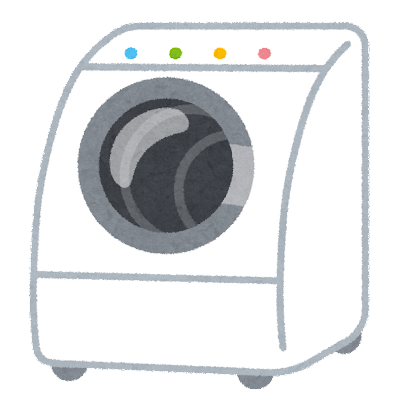
ただ構造的に、ドラム式と比べて縦型は乾燥が苦手である。
私のように乾燥機能を重視した場合は、ドラム式を選んだ方が無難だろう。
しかし、ドラム式を選ぶとしても、中には乾燥が苦手な機種もあるから注意が必要だ。
乾燥方式としてヒーター式、ヒートポンプ式、そしてハイブリッド式がある。
ヒーター式では、直接ヒーターの熱で洗濯物を乾燥させる。
乾燥温度が高温になるので、洗濯物がカラッと乾く反面、衣服へのダメージが心配だ。
ヒートポンプ式は、ヒーターが不要でエアコンのような構造で除湿乾燥させる。
乾燥温度が低温で済むので、衣服へのダメージは少ない反面、ヒーター式のようなカラッとした仕上がりにはならない。
そしてハイブリッド式は、ヒーター式とヒートポンプ式を組み合わせたものだ。
世間一般的には、エコで効率よく乾燥させることが可能なヒートポンプ式が評価されているようだ。
主に上位機種ではヒートポンプ式を、下位機種ではヒーター式を採用されている場合が多い。
しかし私は、ヒーター式を強くオススメしたい!
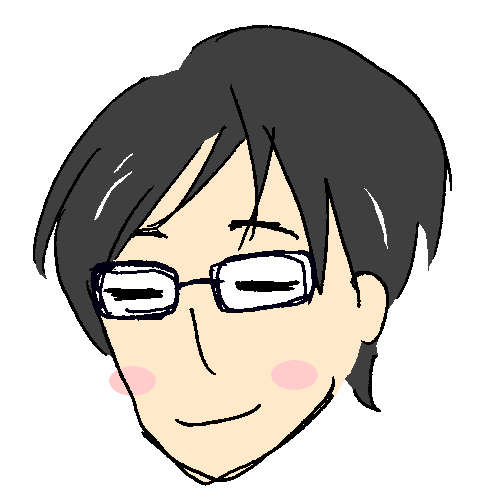
注目する所は、乾燥時の温度である!
コインランドリーの乾燥機を思い出して欲しい。
コインランドリーの乾燥機の多くはガス乾燥機である。
家庭用で多く使われる電気乾燥機よりも高温で乾燥できるため、高速でカラッと仕上げることが可能だ。
また高温で乾燥させることで衣類の雑菌を除菌することが可能である。
梅雨時などに部屋干しして付いてしまった生乾きの臭いは、雑菌の繁殖が原因である。
一度付いてしまった生乾きの臭いは、そう簡単には取ることは出来ない。
しかし高温で乾燥させることで臭いの元を断ち切り、不快な臭いを解消することが出来るのだ。
家庭用でもガス式の乾燥機は存在するのだが、2023年9月現在『洗濯乾燥機』としてラインナップはない。
あくまでも『乾燥機』なので洗濯機からの入れ替えが必要になる。
乾燥力としては魅力的なのだが、全ての家事を「したくない」私としては、洗濯物を入れ替える余計な手間が増えるので選択肢として外れてしまう。
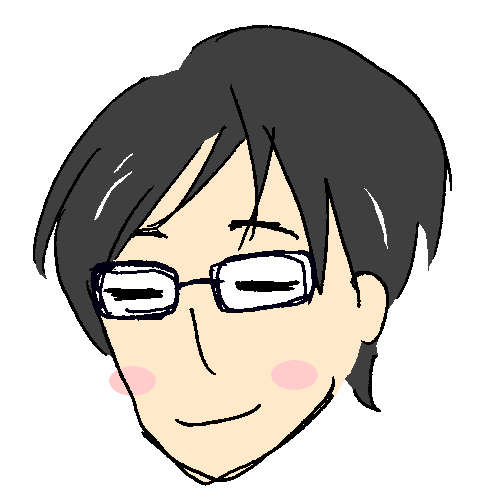
そこでヒーター式をお勧めするのである。
ガス式よりもパワーは劣るが、除菌が可能な高温を出すことも可能である。
そして洗濯乾燥機であれば、洗濯から乾燥まで自動で一貫して行うことが出来る。
一方で、ヒートポンプ式では高温を出すことが出来ず、除菌することが難しい。
従ってヒートポンプ式では、一度生乾きの臭いが付いてしまった衣類は、その後洗濯したとしても臭いがなかなか取れないのである。
洗濯物の臭いが気になる場合がある

今話したように、いくら洗濯乾燥機で乾燥させたとしても乾燥方式の違いにより、生乾きの臭いに悩まされることがある。
確かにヒートポンプ式では、ヒーターを使用せず効率よく乾燥できるため、電気代を低く抑えることが出来る。
そして低温で仕上げることで衣類へのダメージも少なくて済む。
しかしその反面、一度生乾き臭が付いてしまったら、それを除去するのは難しい。
そのため『消臭』だの『抗菌』などを謳った洗濯洗剤を使い、さらには『良い香りのする柔軟剤』で臭いを誤魔化す必要があるのだ。
臭いに関して、もう1点。
購入してすぐに乾燥機能を使う時に注意してほしい臭いがある。
これは取り扱い説明書にも記載されていることなのだが、
購入後しばらくの間、乾燥後に異臭が発生する。
これは、熱によりドアパッキンやゴム部品などから臭いが発生するためで、これが衣類に付着してしまうのだ。
私は2023年春に洗濯乾燥機の買い替えを行ったのだが、久しぶりの買い替えだったのでこの異臭のことをすっかり忘れており、盛大に衣類に異臭を付着させてしまった。
現在はもちろん、乾燥後の異臭は解消されている。
そこで諸君が洗濯乾燥機を購入した場合は、1週間ほどは注意して乾燥機能を使ってほしい。
例えば使い古しのタオルなどを試運転用として最初に乾燥させて、臭いを確認しながら徐々に衣服を投入してもいいかもしれない。
機種による電気代の差が大きい

洗濯乾燥機を導入するに当たって、光熱費も気になるところだろう。
まず最初に断っておくが、通常の洗濯機から洗濯乾燥機へ買い替えた場合、光熱費は上がると思ってもらっていい。
もちろん、洗濯乾燥機を購入したのに乾燥機能をまったく使わないなら話は別だが。
光熱費が上がるのは必然である。
乾燥のための稼働時間が増え、その分の電気代が掛かるからである。
その点に関しては、家事「しない」ことに対する対価と考えてほしい。
何も対価無しに楽をできるほど、世の中甘くは無い!
では、電気代に注目して話を進めていく。
2023年8月時点で、消費電力量1kWh 当たりの電気料金の目安単価は 31円 と言われている。
出典:公益財団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
https://www.eftc.or.jp/qa/#:~:text=現在の目安単価は,必要とされています%E3%80%82
この単価を元にすると、洗濯乾燥運転を1回させた時にかかる電気代は各メーカー・各機種で異なり、おおよそ40〜90円程度かかるようだ。
これは洗濯物の量や種類によって多少変動するものだが、選んだ機種によっては50円程度の違いがあると思っていいだろう。
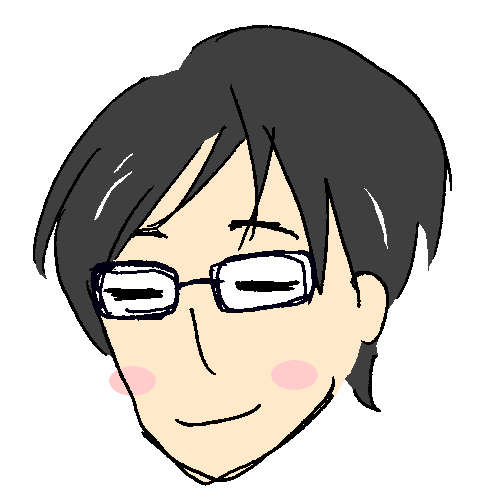
30日で1500円、365日で18,250円の差だ。
「では、電気代が安い機種を選べばいいんだな」と言いたくなる気持ちも分かる。
電気代が安いに越したことは無いし、何よりもエコである。
しかし先ほど、洗濯乾燥機には乾燥方式の違いがあることを説明したが、乾燥方式の違いは電気代にも関わってくる。
ヒーター式は、ヒーターで高温で乾かすため、電気代がかかってしまう。
一方でヒートポンプ式は、効率よく低温で乾かすため、電気代は低く抑えられる。
私がオススメするヒーター式は、高温でカラッと乾きやすいという反面、電気代が高くなる傾向にあるのだ。
一概に、ヒーター式はよく乾いて、ヒートポンプ式は生乾きになる、とは断定できない。
ヒーター式なのに、電気代だけ掛かって、全く乾かない!という場合もあるかもしれない。
いくらよく乾いたとしても、電気代が高すぎるのは嫌だ!と思う人もいるかもしれない。
電気代は購入価格と違って、この先ずっと関係してくる大事な要素である。
そしてこの先、電気料金が上昇していくことも考えられるため、慎重に見極めていきたいはずだ。
ここで、1回の運転時に掛かるだいたいの電気代の計算方法をお教えしよう。
(洗濯時)
洗濯時の消費電力量[Wh]×洗濯時間[時間]×31[円/kWh]÷1000=洗濯時の電気代[円]
(乾燥時)
乾燥時の消費電力量[Wh]×乾燥時間[時間]×31[円/kWh]÷1000=乾燥時の電気代[円]
(合計)
洗濯時の電気代+乾燥時の電気代=1回の運転時に掛かる電気代[円]
消費電力量については、メーカーホームページで各製品ページにある「スペック」や「仕様」を確認すればよい。
またその時に「消費電力[W]」と見間違わないように注意しよう。
ちなみに、現在私が使用している機種は下記である。
日立製、BD-SV120HL
では、電気代を計算してみよう。
(洗濯時)
78[Wh]×0.5[時間]×31[円/kWh]÷1000=1.2[円]
(乾燥時)
1570[Wh]×1.6[時間]×31[円/kWh]÷1000=77.9[円]
(合計)
1.2+77.9=79.1[円]
1回当たりの電気代が約80円というと、他機種と比べると高い機種になると思う。
しかし私は、この電気代も想定した上で購入している。
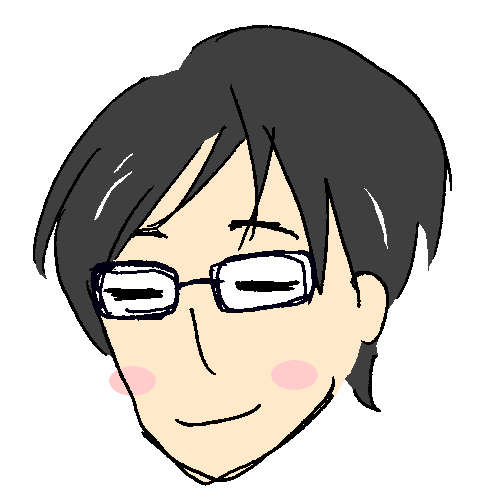
バツグンの乾燥力に期待したからである。
そして実際に購入してみて、期待通りの乾燥力で非常に満足している。
電気代が安く済めばありがたいのは事実なのだが、電気代がいくら安くても洗濯や乾燥の性能が魅力的でなければ意味はない。
理想的な洗濯乾燥機を選ぶためには、電気代もひとつの指標として大事なのだが、電気代だけで比較しないように注意してほしい。
日常的なフィルターの手入れが必要
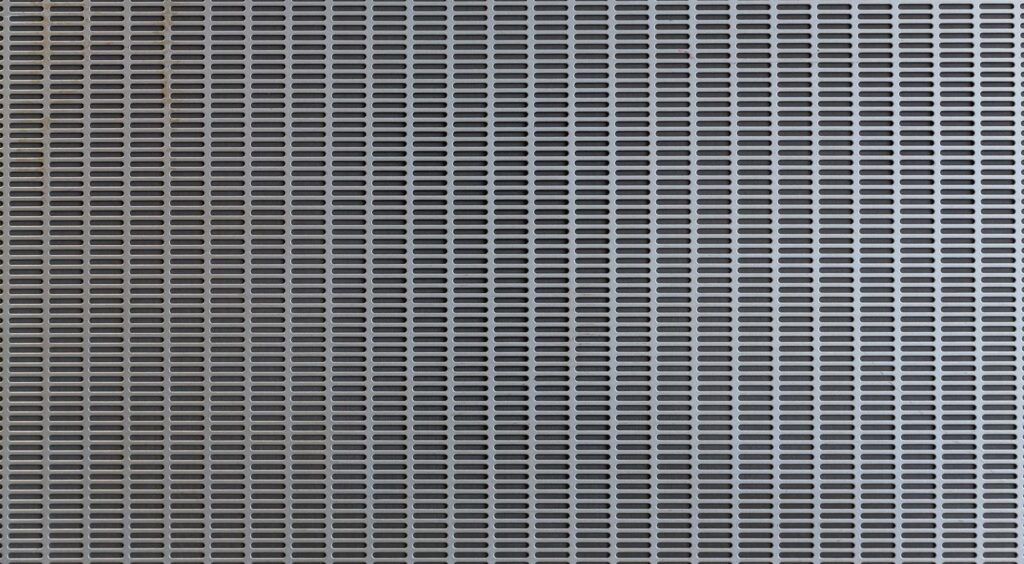
縦型洗濯機には糸くずフィルターなるものが洗濯槽内に設置されていると思う。
洗濯時に洗濯物から出た糸くずやゴミをキャッチするのだが、洗濯乾燥機にも同じようにフィルターが設置されている。
洗濯乾燥機に設置されるフィルターは基本的に2つ。
まず縦型同様に糸くずフィルターがある。
メーカー等によっては、排水フィルターなどと呼び方が変わるかもしれないが、役割は基本的に同じ。
もうひとつに乾燥フィルターがある。
こちらは乾燥時のホコリや糸くずをキャッチする。
これらのフィルターは日常的な手入れ、つまり定期的にゴミを除去をする必要がある。
機種によりフィルターの形状や手入れの頻度・方法は様々だが、概ね糸くずフィルターは週一程度で、乾燥フィルターは乾燥運転の度に手入れの必要がある機種が多いようだ。
週一とか、毎回とか、いかにも面倒そうな手入れの話を聞くと、家事「したくない」諸君は洗濯乾燥機の購入を少しためらってきたのではないだろうか?
しかし安心してほしい。
縦型洗濯機でも同じような手入れが必要なので、さほど手間は変わらないだろう。
さらに、諸君に朗報である。
技術の進歩により、その手入れもどんどん楽になってきているのだ。
たとえば私が今使っている洗濯機、
日立製、BD-SV120HL では、乾燥のたびに手入れが必要だった乾燥フィルターが無いのだ。
代わりに大容量の糸くずフィルターが設置され、約1ヶ月に1回の手入れで済む。
そのようなメンテナンス性にも考慮して、洗濯乾燥機を選ぶことで、理想とする家事「しない」生活に近づけるはずだ。
まとめ

いかがだっただろうか。
今回は8年以上洗濯乾燥機を使ってきた私タンジズムが、実際に経験したトラブルや使うまで気付いていなかったことを紹介してきた。
洗濯乾燥機選びに失敗したくない諸君は、どんなことに気をつけて選べばいいのか迷ってしまうと思う。
そんな諸君は、ぜひ5つの注意点を参考にしてほしい。
◆ 実際の経験をもとにした5つの注意点 ◆
・乾燥が苦手な機種もある
・定期的な修理依頼が必要な機種もある
・機種による電気代の差が大きい
・初めの洗濯物が臭い場合がある
・日常的なフィルターの手入れが必要
これらだけに注意すれば、諸君が理想的な洗濯乾燥機を購入できるかと言われると、違うかもしれない。
しかし知る前と後では、考え方が大きく変わったはずだ。
購入した後に後悔しないためには、自分自身で調べ、そして自分自身で考えるることが重要だ。
今回の記事をもとに、諸君の理想的な洗濯乾燥機を自分自身で見つけだしてほしい。
このまま「したくない」ことにエネルギーを使い続けるより、今変わることに少しだけエネルギーを使った方が、きっと、この先の人生のためになる。
「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」
諸君が「したくない」洗濯から解放されて、「したい」ことで人生を楽しんでもらうことを願って。

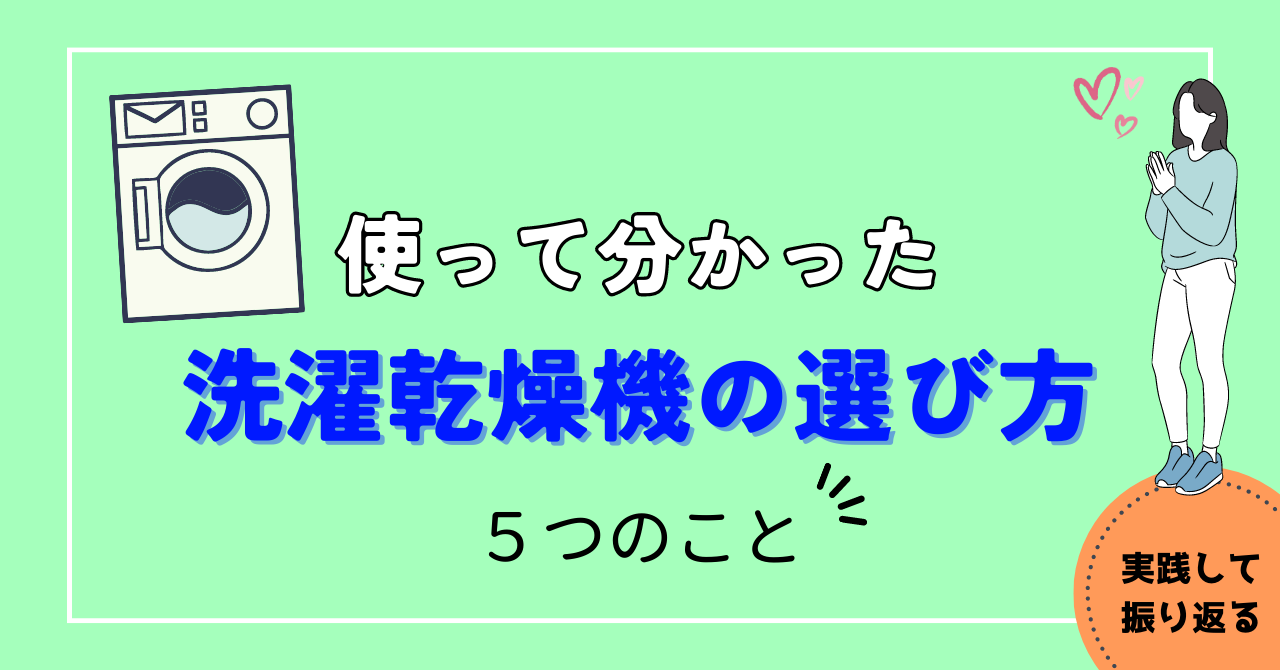
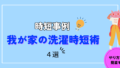
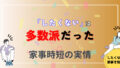
コメント